News最新情報
2024.01.24
「蝶々夫人」記者会見レポート!

芸術文化センター最初の夏のプロデュースオペラとして2006年に上演された「蝶々夫人」。故栗山昌良氏の原演出による美しい舞台が、2024年7月に改訂新制作上演で再び兵庫を感動に包みます。
1月中旬に行われた記者会見において、佐渡裕芸術監督、再演演出の飯塚励生さん、蝶々さん役の迫田美帆さんと高野百合絵さんが登壇し、意気込みを語りました!
佐渡 裕(芸術監督・指揮)
「蝶々夫人」と栗山昌良氏への思い
実はこの「蝶々夫人」は、芸術文化センターが20周年を迎える2025年に取り上げたいと考えていました。栗山昌良先生の年齢を考えて計画を1年早めたのですが、残念ながら昨年、先生が亡くなり、追悼の意味も帯びた2024年の上演となります。
栗山先生と出会ったのは私がまだ19歳の時でした。関西二期会のオペラ公演の最終リハーサルに先輩に呼ばれていくと、急遽、指揮者が見えない合唱のために客席の隅でペンライトを振ってテンポを示す役割を与えられ、言われるがまま振っていたら栗山先生から「邪魔だよ!」とめちゃくちゃ怒られて…というのが最初の思い出です(笑)。そこから26歳まで、関西二期会で副指揮者として栗山先生の演出には何作も立ち会いました。中でも一番印象に残っているのがこの「蝶々夫人」です。また私がブザンソンのコンクールに優勝した後、1992年に関西二期会の本指揮者として振ったのもこの「蝶々夫人」でした。
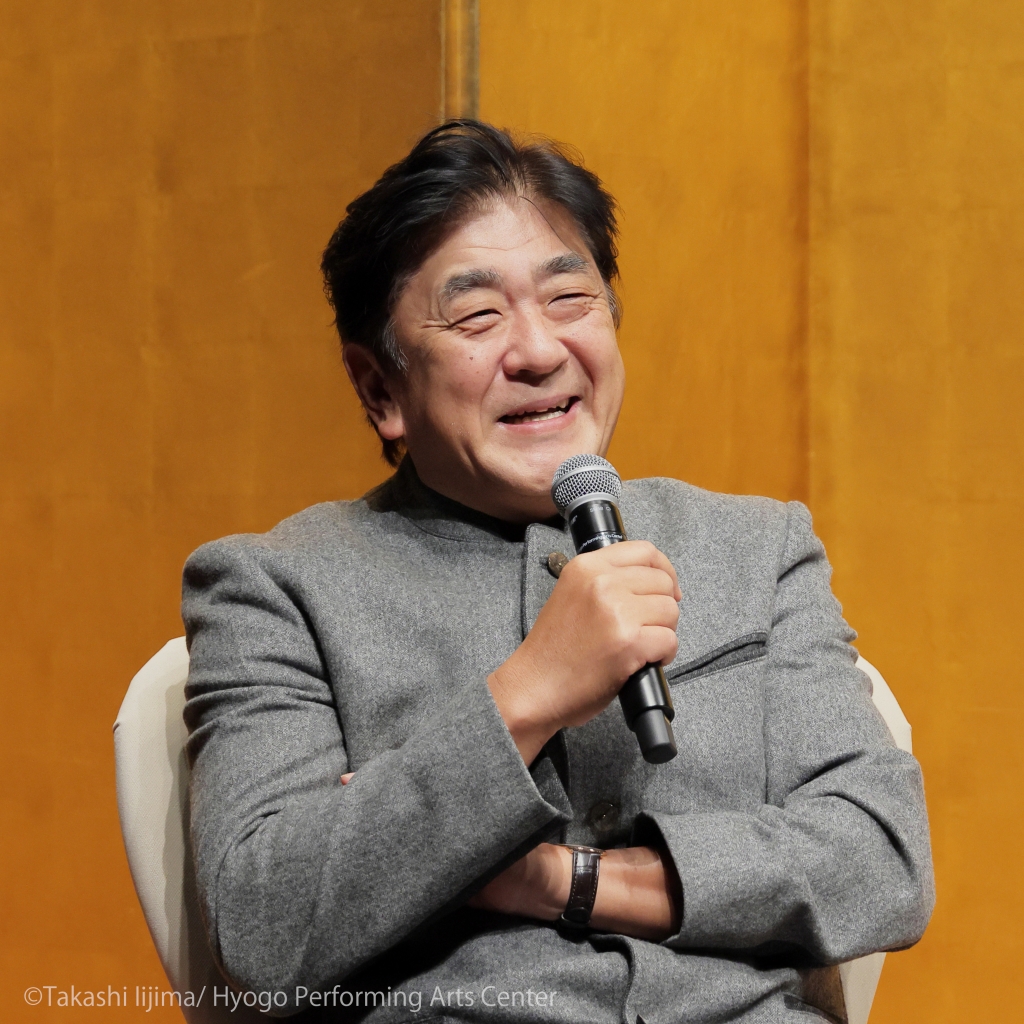
「蝶々夫人」は世界中で上演されていますが、私は海外で「蝶々夫人」を観て、なおさら栗山演出がいかに素晴らしいかを感じました。日本人が日本の舞台を演出しているから納得がいくというだけでなく、音楽的にもドラマとしても、この名作を知り尽くした演出なのです。決して派手な音楽が鳴り響くわけではないのですが、先生の演出によってそれぞれの登場人物像が浮かび上がり、本当にハッとするシーンばかり。“美しさの連続”です。
音楽的には、決してハッピーではありません。冒頭からオーケストラがドラマティックな蝶々さんの人生を表していて、最後に蝶々さんが自刃する場面は非常に激しい音で終わるのですが、いわゆる音楽が終わる音では終わらない。不安定で、「?」がつくような音で終わります。そして実はそのハーモニーから、冒頭の音楽にまた戻れる。ここが、プッチーニの驚くべきところ。つまりこの話は、過去の悲劇ではなく、これからも輪廻していく物語であるという意味が込められています。また、例えば一幕の愛のデュエットは、スローモーションの音楽のなか二人が寄り添っていくよう。このような場面では、蝶々さんにとって、美しい大事な写真アルバムを見ているように音楽が進んでいくと私は思っています。
2024年の上演へ向けて
今回、私とは付き合いの長い飯塚励生さんが、栗山先生が遺した舞台、アイデアを活かして再演演出にあたられます。また、今回は二人のプリマドンナや新たな出演者を迎えます。プッチーニの音楽や、ドラマのあり方は私の中に叩き込まれているので、私からも色々と伝えていきたいし、そこから励生さんと相談し、また歌手たちからもアイデアを受け取りながら、一緒に新しい舞台を作っていきたいと思います。これから新たなオペラファンとなられる方にも、今までのオペラを観てきてくださった皆様にも「やっぱり兵庫芸文のオペラは面白いな!」と思っていただけるものを、自信をもってお届けします。
飯塚励生(再演演出)
圧倒的に美しい栗山氏の舞台を大切に
私は兵庫での2回と、その前の新国立劇場での「蝶々夫人」の上演で、栗山先生の助手を務めました。両者で演出は違いますが、先生は、音楽を信じて音楽を感じながらキャラクターを作られていました。そして、身体の形から、スタイルから、表現・表情を作るのだと毎回言われていました。逆に日常的な演技に対しては批判的で、映像作品のように内面から感情を表そうとすると、心が中に入ってしまい大きく見せられない、舞台の空間を埋めることはできないと、歌手たちにおっしゃっていました。
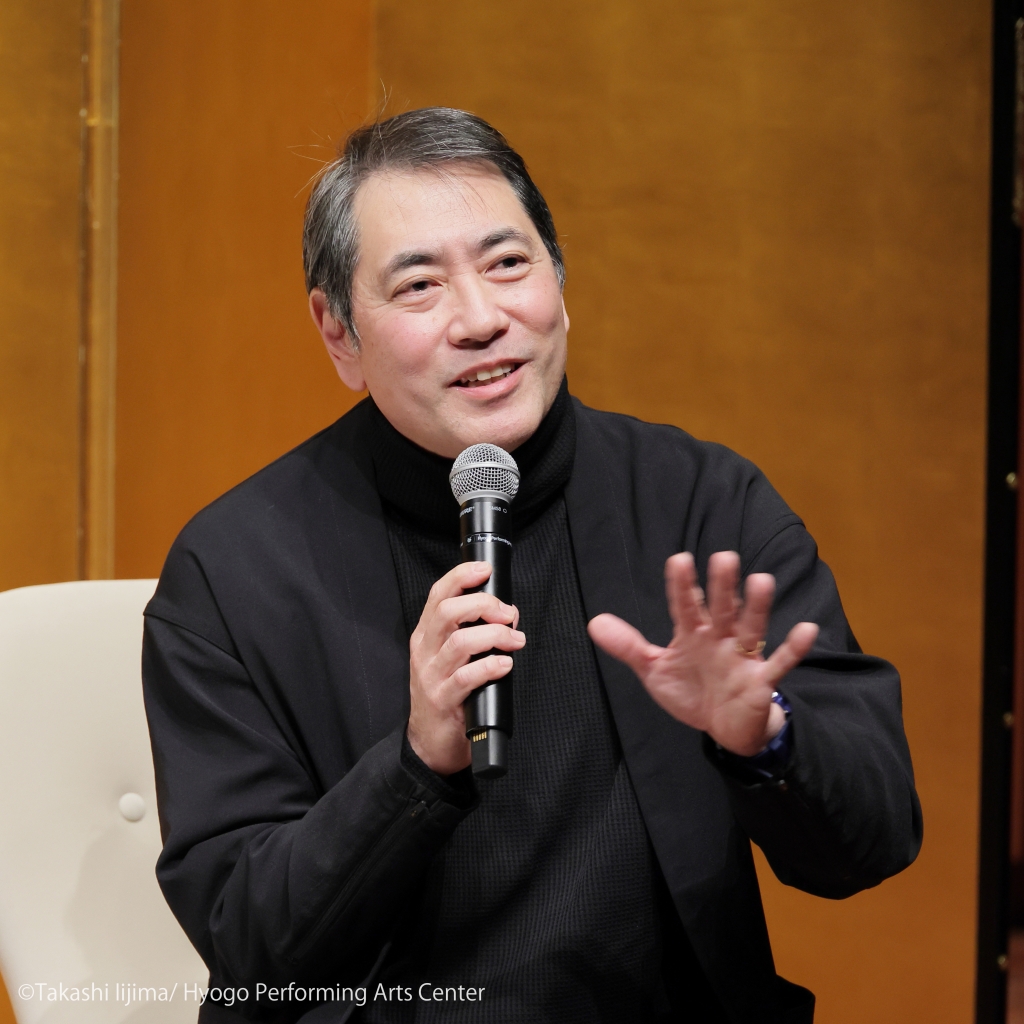
私はちょっとユニークな立場で、日本人の両親のもとニューヨークで生まれ育ったので、やはりアメリカ人、日本人の両方の目から作品を作りたいという思いがありますが、まずは栗山先生のキャラクター作り、非常に美しい人の運び方、形はキープしてぜひ皆様に観ていただきたいと思っています。
迫田美帆(蝶々さん役)
プロデュースオペラ初出演。心に残る蝶々夫人を
本公演に題名役として立たせていただけますこと、心から光栄に思います。
実は、私がこのプロデュースオペラに関わらせていただくのは二度目で、2022年の「ラ・ボエーム」ではカヴァーキャストを務めました。その際、急遽公開リハーサルで歌うことになり、佐渡マエストロとは初対面のような状態で舞台に立ったのです。緊張も不安もある中でしたが、始まるとプッチーニの音楽を通して歌い手の意図を汲み取り、丁寧に寄り添って音楽を作ってくださいました。音楽が進むにつれて、不安や緊張が払拭されて、役にのめり込んでいけるような舞台だったと深く心に残っています。今回はリハーサルの段階からご一緒できるので、非常にワクワクしています。

高野百合絵(蝶々さん役)
大きな挑戦を積み重ね、世界の舞台を目指す
プロデュースオペラには、2021年に「メリー・ウィドウ」ハンナ役で初めて出演しました。オペラ公演の経験もまだ少ない中、稽古現場の皆様が、舞台の中心にいる人物としての表現、立ち振る舞いなどを一から教えてくださり、それが今の私を作っています。2023年の「ドン・ジョヴァンニ」ドンナ・アンナ役での出演の際には、小栗プロデューサーから、「アンナ役はソプラノとして大切な役で、この役を歌えた先にプリマドンナの役が見えてくる」というお声をいただきました。技術面でも精神面でも大変難しい役でしたが、自分の引き出しが何倍にも増えました。

今回、また大きな挑戦として蝶々夫人を務めさせていただくことになりました。最初は不安でしたが、少しずつ、この蝶々さん役を何十年も歌い続けていきたい、この役で世界の舞台も踏みたいという強い意志に変化してきています。
一幕は可憐で純粋無垢な蝶々さん、二幕では母親となり、三幕では凄みさえ感じる芯の強さを見せ、ドラマティックな表現が求められますが、最後まで10代の女性だったということを意識したいと思います。
2024年は世の中が厳しいスタートとなり、特に北陸出身の私は、身近な人が被害に遭っているのを目にして、毎日自分には何ができるのだろうと考えます。公演をご覧になった方が少しでも非日常の世界を味わって、エネルギーが湧いてくるような舞台にできたらと思っています。



